【2012年 第7回】総合格闘家・長谷川秀彦選手 前編
ライフプラン別コラム – プロ格闘家のためのファイナンシャル・プランニング
平野 厚雄(ヒラノ アツオ)⇒プロフィール

3人目のプロ格闘家として登場していただくのは、総合格闘家・長谷川秀彦選手(アカデミア・アーザ水道橋)です。

長谷川選手は、中学校1年生から柔道をはじめ大学まで柔道一本。大学卒業とともに、総合格闘技に転向、その後、デモリッション、パンクラス等のリングで戦績を重ね、2006年には総合格闘技イベント・DEEPにおいて、第2代ウエルター級チャンピオンに輝きました。そして、その後は国内最大級の総合格闘技イベントである「やれんのか!」にも参戦し、世界的にも有名な格闘家・桜井マッハ速人選手と対戦しております。その他にも、現在、UFCのトップ選手として活躍している岡見勇信選手、キム・ドンヒョン選手とも名勝負を繰り広げています。長谷川選手は、日本を代表する中量級の総合格闘家の1人です
プロ格闘家としてとても重要なこと
今回の取材の中で、長谷川選手がプロ格闘家としてとても重要なことが1つある!と強調されていたことがあります。それは、以下のことです。
![]()
小中規模の興業の場合、主催者は、出場選手に何を期待しているかというと2点あると考えられます。1点目は、その選手の強さや観客を沸かせる試合をしてくれるということ、つまり格闘家としての「強さ」です。そして、もう1点は、その選手がどのくらいチケットをさばいてくれるのか(売ってくれるのか)?という「チケット販売能力」です。なぜなら、主催者にとっては、その興業のチケットが売れるかどうかは、最重要ポイントであるからです。
例えば、どちらも同じくらいの強さのA選手とB選手がいて、A選手はチケットを10枚しか売ってくれそうにない、一方、Bさんは、チケットを100 枚売ってくれそうだ・・・という話になった場合、主催者はB選手にオファーするということです。もちろん、絶対という話ではありませんが、選手の「チケット販売能力」というのは、主催者からすると、とても重要なファクターの1つなのです。また、興業によっては、選手のファイトマネーが、さばいたチケット枚数(売上)に連動する、ということもあります。つまり、選手にとっても「チケット販売能力」が高いということはプラスになるのです。
このように考えると、「チケット販売能力」は、「フルコミッション型の保険営業」と似ていると思います。自分から「チケット」という商品を買ってもらう、そして、その売上が自分の収入や出場機会の増加に直結するということです。「チケット販売能力」を「フルコミッション型の保険営業」と同じように考えると、その能力を高めるためには、普段から自分という人間を知ってもらい、周囲の人間と良い関係を作っておくことが大切ということです。普段、何の付き合いも無いのに、いきなり「試合が決まったのでチケット買ってください!」と言っても、それは無理な話ですよね。
結局のところ「人脈形成」が重要
つまり、プロ格闘家としては「強さ」と「チケット販売能力」の2つが大事になるわけですが(ちなみに、わたくしの知り合いの選手は、ある団体の主催者から「チケット100枚売ることができれば試合組んであげるよ~。」と言われたこともあるそうです)、では、その「チケット販売能力」を高めるためにはどのようにすれば良いのでしょうか?私は、結局のところ「人脈形成」に繋がってくると考えます。そして、プロ格闘家にとってその人脈形成の場としては、以下の4つが考えられると思います。
① 道場での人脈
② 勤務先での人脈
③ 学生時代の人脈(友人)
④ 異業種交流会での人脈
①~③については、分かりやすい話だと思いますので省略します。今回は「④異業種交流会での人脈作り」について考えたいと思います。昨今、「朝活」という言葉に代表されるように、様々な場所で異業種交流会や勉強会が開かれています。そして、経営者やビジネスパーソンたちが、名刺交換等して人脈形成に励んでいるわけです。そこで、あるプロ格闘家は、経営者があつまる交流会に定期的に参加し、人脈作りに勤しんでいる・・・なんて話を聞いたことがあります。では、なぜそのプロ格闘家は、異業種交流会に参加するのでしょうか?
後編へ続く。





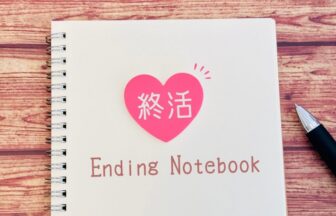


この記事へのコメントはありません。