【2012年 第2回 】北海道のお受験事情 エリア別コラム – 地域:北海道東北
恩田 雅之(オンダ マサユキ)⇒プロフィール
-225x300.jpg)
1月14日、15日、全国709ヶ所でセンター試験が実施されました。北海道では25ヶ所で実施。
今回は、地理・歴史・公民で受験科目を選ぶ方式が変更になり、問題の配布や受験前の説明に手間取り開始時間が遅れるトラブルが各地でありました。
センター試験 トラブル続発
それによる再試験の対象者は、全国で3452人、北海道では266人でした。
問題点が明らかになるにつれ、他の国の制度のようにセンター試験も度重なる変更から制度疲労を起こしているように感じました。
北海道の受験状況について
まずは、平成22年度の道内の学校数をみてみましょう。データは、北海道教育委員会のホームページを参照しました。

上記の表を見ていただきますと、北海道の特徴として小中学校において、私立の比率が公立に比べて極端に少ないことです。その中で国立の4校は、北海道教育大が札幌校、旭川校、釧路校にそれぞれ付属小学校、付属中学の数字になります。ただし、北海道教育大には付属高校はありません。
小学校受験は、北海道教育大付属小学校への受験が大半になります。また、それぞれの付属小学がある地域に居住していることが受験資格の中にあります。
中学受験は、北海道教育大付属中学への受験以外では、道立の中高一貫校 北海道登別明日中等教学校は2.5倍前後の高倍率になっています。私立でも、中高一貫教育を実施している学校に人気があるようです。
また、北海道は大学までの付属中学が北星学園、東海大など数えるくらいしかないと言った特色があります。

高校受験の傾向としては、道内に私立大学付属の高校が少ないため、その地域の公立の難関校を目指す傾向があります。例えば、北海道教育委員会の1/27の発表では、札幌市があります石狩管内では、東高、西高、南高、北高が難関校になり普通科の平均倍率が1.06倍のところ1.4倍の高倍率になっています。
私は、札幌の北区の地下鉄北34条駅の近くに住んでいます。10年ほど前からマンションの増加に伴い小中学校の学力レベルが上がってきました。
北高 → 北大 を狙うご家庭が増えたようです。
最近の特徴として、特定の科目に力を入れる学科や資格の習得、就職に強い学科の倍率が高くなる傾向があります。北海道の高校進学率は、98.8%と全国均98.2%より若干高くなりますが、大学進学率では、全国平均が54.4%に比べ40.4%と低くなります。
この数字からも高校の職業科の倍率が高くなる傾向校がわかります。

大学受験に関しては、大学入試センターの発表によると、平成24年度の全国では55万5537人の志願者で前年より▲0.6%(3447人減)、北海道は1万9772人で前年比▲2.4%(493人減)でした。
北海道の大学の傾向としては、首都圏のように国公立と私立(早稲田、慶応、上智など)の偏差値が拮抗するようなことは無く、北海道大学を筆頭として国公立 → 私立という構造になっています。
最近の受験前の傾向として、大学が頻繁にオープンキャンパスを開き、それぞれ学部の特徴や就職先、就職率等を熱心に説明しています。 志望校を決める時の参考になると思います。積極的に参加することをお勧めします。
今後の受験状況について
平成22年度の国勢調査による北海道の12歳、15歳、18歳の人口は以下の表のようになります。
平成27年の数字は、平成22年時点で7歳、10歳、13歳の人口を使用しています。どの年齢も5年間で1割前後、受験者数が減ることが予想されます。

このような人口の推移で考えますと、高校、大学とも中堅クラスであまり特色のないところでは、学生数の確保に苦労するように思います。
北海道の看板大学
北海道の看板大学は、知名度と合格の難易度、キャンパスの広さで選ぶと北海道大学になります。
しかし、食料自給率(カロリーベース)40%の日本の中で、200%前後の食料自給率(カロリーベース)がある北海道、TPP参加を奇貨として、農業(畜産・酪農)に特化した大学、国立の帯広畜産大学や私立の酪農学園大学にも、私個人としては、頑張っていいただきたいと思っています。




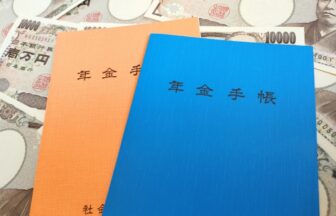




この記事へのコメントはありません。