マイアドバイザー® 池田龍也 (イケダ タツヤ)さん による月1回の連載コラムです。
目次
【第19回】 池田龍也 の ちょっと気になるニュースから ~トランプ関税戦争とリーマンショック~
池田龍也⇒プロフィール
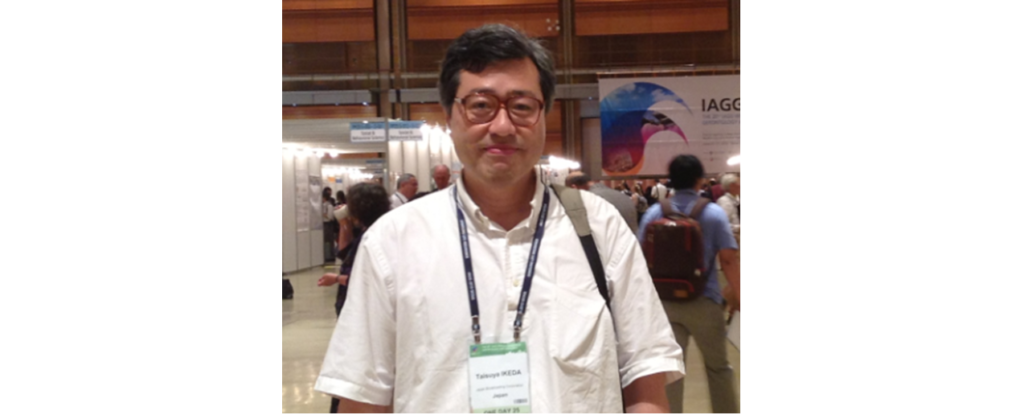
▼ トランプ関税~米中貿易戦争再燃~
トランプ関税に関する米中貿易戦争が、再び過熱という感じになってきました。
<トランプ氏「対中関税100%追加」 11月1日から、輸出規制に対抗>(2025年10月11日)
トランプ大統領は10日、中国からの輸入品にかける関税を11月1日から100%上乗せすると表明。また、米国製の「あらゆる重要なソフトウェア」を対象に輸出規制を11月1日から始めるとも表明。
このコラムを書いている時点では、米中首脳会談がこれから開かれる予定ですが、基本構造は急には変わりません。これはアメリカの覇権に対して、中国が挑戦している、それを抑えようとしているのが今のアメリカだ、という構図をわかりやすく説明している本に出会いました。中国が経済発展を謳歌してきた時代は終わったという指摘です。
その本は「世界秩序が変わるとき」(文春新書)です。著者はワシントン在住の投資コンサルティング会社共同経営者、齋藤ジン氏で、その的確な分析や見通しには定評があり、アメリカのヘッジファンドのつわもの達からも一目置かれている存在だそうです。傾聴すべきポイントがいくつもあるのでご紹介していきたいと思います。
▼ トランプ政権には明確な対中戦略がある
トランプ政権にはしっかりと熟慮した対中政策がもともとあった。
- 貿易戦争
- 戦略的資源(ハイテク製品、天然資源など)の中国依存の低下
- 中国に対する米国の「イノベーション優位性」の維持
- 地域パートナーの対中国の経済・防衛能力強化
- 米日豪印による安全保障対話の枠組み「QUAD」の強化
- アジア同盟諸国への技術支援を拡大し、中国の「一帯一路イニシアティブ」に対抗する
などを包括的に進めることを狙っていた、というのです。
▼ 潮目は変わった(新自由主義の時代の終焉)
1990年代、アメリカは急速に新自由主義が席巻、世界標準に。新自由主義の考え方は、「小さな政府」、市場に任せる、グローバル経済の中で、経済相互依存が進めば紛争もなくなる、という。これが、トランプ大統領の登場で、まったく逆回転し始めている、というのが齋藤氏の指摘です。

アメリカの有権者の約45%が求めているのは、「既存のシステムを壊してくれ」ということ。新自由主義がもたらした格差や鬱積した感情をトランプは直感的につかみ、見逃さなかった、トランプ現象は新自由主義という既存のシステムへの信認の揺らぎである、ととらえている、というのです。
▼ リーマンショックは今の米中貿易戦争につながる
トランプ現象、米中貿易戦争は、そういう時代の大きな転換期に表れた現象ではないかというのが、齋藤氏の論点です。
リーマンショックというと、2008年、いまから17年も前の古い話、終わった話という方も多いかもしれませんが、あのリーマンショックがいまの米中貿易戦争につながっているといいます。齋藤氏は、あのリーマンショックが、まずは大きな時代の転換点だったといいます。
▼ キーワードは「ゲームチェンジ」
リーマンショック、金融危機の勃発は、市場に任せておけばうまくいく、という考え方が正しくないことを証明しました。アメリカ政府は、リーマンショックで信用不安が急拡大すると、それからわずか1か月で緊急経済安定化法を成立させ、巨額の公的資金を投入しました。「小さな政府」の新自由主義から、政府が介入する「大きな政府」への転換点でした。

そしてトランプ大統領の登場で、さらにそれが加速、自由貿易の時代は完全に過去のものに、アメリカからすれば「不均衡の是正」という流れになり、現実の米中貿易戦争、関税戦争、という動きにつながっているというわけです。
▼ 中国が謳歌してきた世界は様変わりした
中国経済はこれからどうなるのか。その新自由主義、グローバル経済、自由貿易体制の中で、最大の恩恵を受けた国のひとつが中国でした。
中国は自国への輸入は管理しながら、アメリカや世界市場へは、輸出をどんどん増やして経済成長を実現しました。自由貿易体制を追い風にして、世界第二位の経済大国となったわけですが、その流れは潮目が変わり、これまで通りのやり方は許されなくなっている、というのが現状だということです。トランプ大統領になって、アメリカへの覇権に挑戦する中国は許さないという流れになっているからです。
中国への締め付けが厳しくなる中で、中国経済を支えていた外からの投資は急激に細くなっています。
中国が発表した対中直接投資は2023年330億ドル(約5兆円)で前年から8割減少、ピークだった2021年の3440億ドルと比べると1割弱まで落ち込んだそうです。国内の不動産バブルは崩壊し、中国経済を牽引してきた輸出や外国からの投資もこれからどうなるのか、内憂外患という状況です。
▼ これからの世界経済
齋藤氏の見立てでは、時代は大きな転換点を迎えている中で、「アメリカは中国を封じ込めるために『強い日本』の協力が不可欠になっている。冷戦の時の米ソ対立の中で「『強い日本』が求められたのと同じ状況になっている」と分析しています。日本には順風が吹いている、復活のチャンスが訪れている、というわけです。
齋藤氏の著書は、いまのトランプ現象をどうとらえたらいいのか、ひとつの重要な視点を提供してくれます。トランプ劇場の目まぐるしく動く展開も、実は大きな歴史の流れで見れば、市場に任せる新自由主義から、政府が関与する「大きな政府」の経済運営に変えていく大きな転換点の動きとみることができるという視点です。「アメリカを再び偉大にする」というキャッチフレーズも、それを分かり易く表現したものという気がします。ますますトランプ劇場から目を離せなくなってきました。
(以下、ご参考情報)
ご興味がある方は、リーマンショックに関する映画やドラマがたくさんありますのでご紹介します。
上記のような流れをふまえてみると、なんだか歴史の転換点で、市場を操っていると自信満々だった選ばれし者たちが、市場に逆襲されてしまう、そして右往左往するしかなかったというように見えてくるから不思議です。
・「リーマンブラザーズ 最後の四日間」2009
リーマンショックの翌年公開の映画。サブプライムローンのリスクが時々刻々表面化していく恐ろしさを淡々を描いている。投資銀行の幹部たちが腹の探り合いをしながら右往左往する姿がリアル。
・「インサイド・ジョッブ」2010
サブプライムローンの仕組みなども詳しく説明した後、関係者の証言でつづるドキュメンタリー。
・「マージンコール」2011
リーマンブラザーズをモデルにしたといわれる巨大投資銀行の内幕を描いている。危機を訴えても、目の前の現実にならないと、危機発生の直前まで動かない人々。
・「ザ・フロー」2011
リーマンショックを経験した様々な立場の人たちの証言でたどるドキュメンタリー。








この記事へのコメントはありません。