マイアドバイザー® 池田龍也 (イケダ タツヤ)さん による月1回の連載コラムです。
目次
【第15回】 池田龍也 の ちょっと気になるニュースから 「中国ってそんなにすごいの?
~中国になぜ?トランプ関税戦争の矛先~」
池田龍也⇒プロフィール
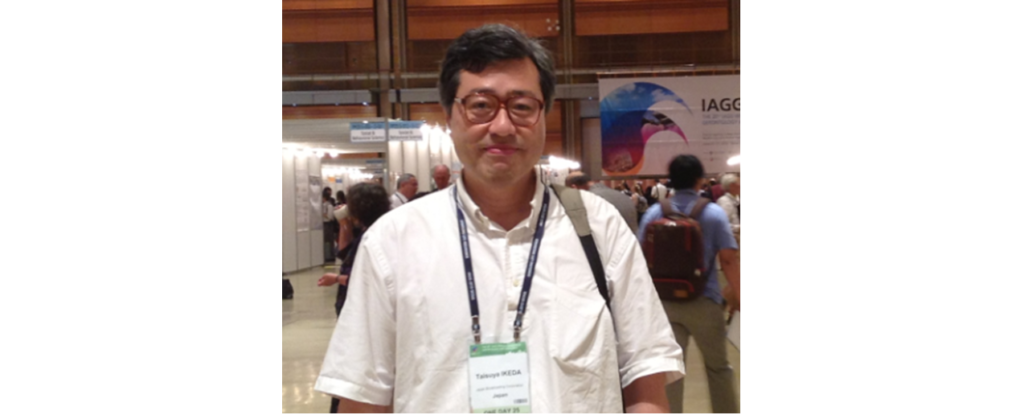
▼ 宍道湖のシジミパックは中国産
島根の宍道湖に行ってきました。「宍道湖にいったらシジミ」ということで、お土産にシジミを買おうと思ったら、なんとシジミの原産地、中国というパックが多くて「え~!!そんなことになっているんだあ」とびっくり。地元宍道湖産の「大和シジミ」ときちんと書いてあるパックを選んで買って帰ったという次第。
中国の存在感は、いまや我々の生活のいたるところに浸透しています。
▼ 米中貿易戦争
さて今回は、トランプ関税戦争の背景について、ちょっと考えてみたいと思います。トランプ関税戦争は、実は中国との「闘い」という指摘もあります。トランプ大統領特有の「ディール」なのかも知れないですが、中国との関係をどうするのか、米中関係の今後はどうなるのか、世界経済の今後を左右する大きなテーマであることは間違いありません。
▼ 米中対決 ひとまず沈静化
ニュース
<アメリカと中国、貿易枠組み合意>
2025年6月12日
米中の高官が貿易摩擦を緩和するための枠組みに原則合意したことを受けて、トランプ大統領は自身のソーシャルメディアで、「合意は成立した」と言及。
中国はアメリカ企業に対し、磁石やレアアース(希土類)を供給することで合意。一方、アメリカ側は中国人留学生のビザ(査証)を取り消すとした方針を撤回する方向。アメリカと中国は10日、ロンドンで2日間にわたる集中的な協議の結果、この枠組み合意に。
▼ 対決なのか共存なのか
交渉にあたっているアメリカのベッセント財務長官は、以下のように語っています。
「どちらの側もデカップリングは望んでいない」
「アメリカは精密製造業が壊滅状態にあり、これを取り戻そうとしている。一方で中国は製造業が過剰生産の状態にありバランスを欠いている。消費に依拠した経済へと移行するとしているが、実現できていない。もしアメリカと中国がより公正な貿易をすれば、共に再均衡をはかるチャンスが生まれる」
要は、アメリカの巨額の対中貿易赤字をどうにかするために、貿易関係を再構築し、米中両国の利益につなげるようにしたいということのようです。共存共栄の道を模索している、というわけです。
▼ 鄧小平の先見の明~中国のこの30年~
鄧小平は、いまから50年近く前の1978年、日本訪問の際、次のように語りました。今世紀末というのは20世紀末、ということです。
「(中国の)今世紀末までに実現する四つの近代化とは、その頃に世界の先進レベルに近づくことを意味している。中国が近代化を実現するためには、正しい政策を持ち、学習につとめ、世界の先進国の管理方法を取り入れてわれわれの発展の出発点としなければならない。まず、自分たちが立ち遅れているということを認め、素直に立ち遅れを認めれば希望が持てる」
その後、1990年代、鄧小平が豊かになれるものから豊かになれといって、開放経済、経済の自由化を推し進めたところから中国経済の発展はスタートしました。日本の経済界も、惜しみなく中国を支援した時代がありました。
▼ 2000年「世界の工場」といわれる
鄧小平がめざした通り、中国は20世紀末頃には「世界の工場」といわれるようになり、いまや世界第二位の経済大国の地位を確固たるものにしています。
2000年前後、中国企業の海外進出が徐々に始まっていました。その頃、東南アジアにも中国企業が進出し始めていましたし、当時インドのIT産業の中心地だった南部、バンガロール(ベンガルール)に取材に行った時、中国の通信大手「華為」(ファーウェイ)がすでに研究開発拠点を作っていたのにびっくりした記憶があります。「華為」はその後急成長を遂げ、いまや世界有数の通信企業になっていることはご承知のとおりです。今思えば、2000年前後、あるいはそれ以前から、着々と準備を進めてきた、数々の中国企業が、今日の中国の世界市場での躍進を支えているわけです。
▼ 発展途上国の経済発展パターン
ある国がこれから国づくりをしようとする場合以下のような経緯をたどります。
・国内産業もあまり育っていない状態からのスタート
・まずは外国からの投資を呼び込み産業を育てていく
・軽工業から重工業へ(主力がIT産業のケースもあります)
・製品を輸出に振り向けて資金を稼いでいく
・自国産業も徐々に育っていき経済が自立していく
・それとともに国民もだんだん豊かになり購買力、国内市場も育ってくる
このサイクルがうまく回り始めれば経済成長が加速していくわけです。日本の戦後の経済成長、東南アジア各国の経済政策も、大なり小なりこのような流れになっています。
この成長の方程式を忠実に実現してきたのが中国でした。30年40年、営々と築き上げてきた産業力が結果的に、中国の競争力を生み出し、中国からアメリカへの輸出増加につながって、アメリカの対中貿易赤字になっているわけです。この状況を変えるといっても、関税だけでこの貿易関係を逆転、あるいは均衡化するのは一朝一夕には無理であろうというのは、だれの目からも見ても明らかだと思います。
▼ 世界の港はいまや中国が席巻
この表は、世界の港のコンテナ扱い量の一覧です。中国の経済力の成長の勢いがどれほどすさまじいのか、一目瞭然です。国土交通省の資料です。
国土交通省の資料より
「世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング」
https://www.mlit.go.jp/statistics/details/content/001517678.pdf
この40年の激変ぶり、ご覧いただけましたでしょうか。上位10位をみてみると、
1980年 中国本土の港はゼロ
2022年 中国の港7か所(香港含む)
中国の貿易が急速に活発になったことがこの表を見ても一目瞭然です。
それから取扱量です。
1980年 トップのニューヨーク 195万個
2022年 トップの上海 4730万個
取扱量でも、この40年間に、とてつもない拡大をしていることが分かります。冷戦終了後、東西の垣根がなくなり、いわゆるグローバル経済の時代に突入、そこに生産国としても消費国としても中国が登場、いまやその存在感はとてつもなく大きなものになっています。
▼ 中国はどこへ行く、世界はどこへ行く
中国は、長く続いた欧米各国(日本も含め)の支配から独立したあと、1997年、およそ100年かけて香港を回収、その後劇的な変貌を遂げ「世界の工場」からGDP世界第二位の経済大国になった今、どこへ行くのでしょうか。少なくとも中国なしに世界経済を語ることはもちろん、米中関係の安定なしに世界経済が安定することもあり得ない状況であることは明白です。
ただ昨今の状況を見ていると、世界の大国同士が、利害をむき出しにして、妥協点や解決策を見出すのを難しくしている現状もあり、利害をむき出しにしながらも、双方が大きなマイナスにはならないという選択肢があるのかどうか、なんだか微妙なバランスの中で、世界情勢の行方が混沌としているように見えます。
ご参考に筆者がまとめた中国経済の現代史一覧年表を末尾に置いておきます。ご興味がある方はご覧になっていただければと思います。

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73767?pno=2&site=nli








この記事へのコメントはありません。