マイアドバイザー® 顧問 岡本英夫 (オカモト ヒデオ)さん による月1回の連載コラムです。
ファイナンシャル・アドバイザー(近代セールス社;2022年春号以降休刊)の初代編集長として、同誌でも寄稿されていたエッセイの続編的な意味合いのあるコラムとなります。
岡本 英夫 ⇒ プロフィール
相続税法による養子の数の制限
相続税を計算する際、法定相続人数に参入できる養子の数に制限が設けられたのは、1988年のことである。
これにより、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数にカウントできなくなった。
これは、子の配偶者や孫と養子縁組を行うことで、各人の課税価格の合計額から差し引ける基礎控除額を増やし、相続税を回避しようとする行為を規制するためであった。
当時、改正前の基礎控除額は「2,000万円+400万円×法定相続人の数」であった。
法定相続人が配偶者と子2人なら3,200万円が基礎控除額だが、子の配偶者や孫と養子縁組を行い、法定相続人の数を10人にすると6,000万円が基礎控除額として課税価格の合計額から差し引ける。
表1. 相続税の基礎控除額の計算例
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額の計算式 | 基礎控除額(万円) |
| 3人(配偶者+子2人) | 2,000 + 400 × 3 | 3,200 |
| 10人(養子縁組多数) | 2,000 + 400 × 10 | 6,000 |
そして相続税の総額を計算する際には、基礎控除額を差し引いた後の「課税される遺産の総額」を法定相続分で按分した額に相続税率を適用することになる。
配偶者と子2人なら、配偶者2分の1と子各4分の1が按分割合だが、子が10人となれば配偶者2分の1はともかく、子は2分の1を10人で分けるため、20分の1となり、適用税率が著しく低下する。
課税される遺産の総額が1億円であれば、配偶者は5,000万円だが、子の仮の取得金額は2,500万円から500万円に激減し、乗じる税率は最低税率となる。
さらに養子に未成年者がいる場合、最終段階で未成年者控除も利用できる。
このように、1988年までの相続税対策では養子縁組が頻繁に利用されていたのである。
表2. 法定相続人(子)の税額例
| 例 | 取得金額 | 税率 | 控除額 | 計算式 | 税額 |
| 子2人の場合 | 2,500万円 | 15% | 50万円 | 2,500万円 × 15% – 50万円 | 325万円 |
| 子10人の場合 | 500万円 | 10% | 0円 | 500万円 × 10% | 50万円 |
民法上、養子縁組に制限はない
1988年当時、この養子縁組による租税回避行為の否認の改正は大きな話題となった。
そのため、養子縁組そのものについても、実子がいる場合1人、いない場合2人までという相続税法の規程が一人歩きしてしまっていた。
しかし、民法上は養子の数に制限はなく、何人養子を取っても認められる。
これらの点について、近代FP協会の顧問であった柴原一税理士にFP養成研修で解説をお願いした。以下はその内容である。
解説1「一般法と特別法」
民法は一般法、相続税法は特別法である。
一般法とは適用対象がより広い法律、特別法とは適用対象が特定されている法律である。
民法に定める相続の規程は広く通用するが、相続税については特別法である相続税法が優先する。
民法上、養子縁組に人数の制限はないが、相続税法の改正により、相続税を計算するときに限り、養子の数に制限が加えられることになった。
また、民法では、相続放棄者は初めからいなかったものとみなされ相続人とはならないが、相続税法では相続放棄者がいても、その放棄はなかったものとして取り扱う。
相続放棄者は相続財産を取得することはないが、相続税の計算過程ではこれを含めて計算し、相続税の総額を算出する。
ただし、各人の算出税額を算出する際には取得価額がないため、相続税額は算出されない。
表3. 一般法と特別法の違い
| 法律名 | 適用範囲 | 養子人数制限 |
| 民法 | 一般 | 制限なし |
| 相続税法 | 特別(税法) | 制限あり |
解説2「法律不遡及の原則」
もうひとつ知っておいてほしいことがある。法律不遡及の原則である。
これは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという原則である。
原則であるから過去のある時点にさかのぼって適用する遡及適用もないわけではないが、あくまで例外である。特に刑罰では、遡及適用は憲法において禁じられている。
これを「刑罰法規不遡及の原則」という。
養子の数の制限前には、税理士や金融機関等のアドバイスにより、かなりの数の相続税対策としての養子縁組が行われていた。
すでに発生した相続については不遡及の原則によりセーフだが、改正相続税法の施行日以降の相続では、実子がいる場合1人、いない場合2人までの効果しかなくなった。
不要となった養子縁組の解消をどうするか、相続税対策の見直しなどをめぐり、多くの問題が生じたのである。
表4. 法定相続人の養子の人数制限
| 被相続人の実子の有無 | 法定相続人に含めることができる養子の人数 |
| 実子あり | 1人 |
| 実子なし | 2人 |
年金改正はとくに注意が必要
FP業務関連では、一般法では民法や商法、特別法では相続税法や国民年金法等が頻繁に改正されるが、改正法案等を読む際に重視してほしいのはその「施行時期」である。
法令は施行と同時にその効力を発揮するが、原則として将来に向かって適用されるものであり、過去の出来事には適用されない。
また、遡及適用や経過措置がある場合は特に注意が必要である。
本年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が通常国会に提出された。
今回の改正案では、被用者年金の適用拡大や在職老齢年金、遺族年金等の改正等が行われる予定だが、法案段階からその施行時期が異なっている。
改正内容だけでなく、施行時期にも注意してほしい。施行日までは現在の法律が適用される。
勘違いのないようにしたいものである。





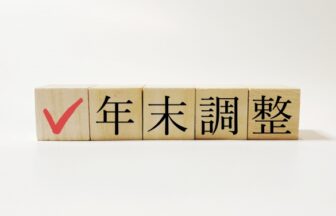



この記事へのコメントはありません。