【 2009年 第 3 回 】海の文化圏と陸の文化圏 もう一つの日中関係 黒潮枢軸
大山 宜男(オオヤマ ノブオ)
かみ合わない食の議論
私の友人に文化人類学的物知り博士で中国本土フリークのM君が居ます。南シナ海、台湾、沖縄、日本列島へと繋がる「黒潮文化圏」を愛する私と、羊の肉を好む新疆省、モンゴル、朝鮮半島(といった彼の言う)「騎馬民族圏」を愛するM君と、食の議論はいつもかみ合わなかったのです。
私の好きな香辛料はワサビ、カラシ、土生姜、黒胡椒、苦手な香辛料は赤唐辛子、生ニンニク、白胡椒。
総じてたんぱく質は酒の肴にあうが、食の道は焼いたりスモークしたりする以外に3種類のユニークなたんぱく質処理法を用意しているとのこと。
生で食うこと、干物にすること、醗酵させること。私は生と干物が好きだが醗酵モノは少々苦手。M君によると香辛料、たんぱく質の処理法の嗜好において、私は騎馬民族失格で典型的な海洋民族とのこと。まず、私の好きな香辛料は総じてアタマの先にビーンと来るが、苦手とする香辛料は胃腸にドーンと来るといいます。またどちらかと言えば前者は身体を冷やし、後者は暖めるものとのこと。また、醗酵系の処理をするのは沿海部よりは内陸部が多いとのことでもありました。M君のこの解説、科学的かどうかは知りませんが、私は納得しています。
食文化から見ても中国は一つではない
そう言えば、香港人の嗜好も海洋民族型に似ていると思います。日本人は多分南方系海洋民族と北方系騎馬民族が混じっているのでM君のようなウラルアルタイ語系の食物が刺身より好きな人も居ます。
この視点=食文化から中国を見ても、中国は一つではありません。広東省や福建省、上海周辺、大連周辺の人たちは海の幸が大好きですが、北京や四川では大分様子を異にします。
その意味では私の観察では、黒潮文化圏、華北農業圏、北西騎馬民族圏の3つの「食の国」かなと思います。
広東語と普通語(中国語)も全然違う
広東語と普通語(中国語)はきっと英語とドイツ語より違うのだろうかとイメージを持ったりします。「サンキュー」と「ダンケ」は似ていますが、「ンコイ」と「シェーシェー」は全然違います。普通語は4声ですが、広東語は6声あるという人もいるし8声という人も居ます。こうなると殆どドレミファソラシドくらいの高低があるので、音楽を聴いているようなものともいえます。
広東語が普通語に較べて音の抑揚が上方の日本語に近いように感じるのは私だけでしょうか?代表的なのが「山田さん」「鈴木さん」という時の「さん」です。苗字が一文字の姓の人には日本語と同じように「陳さん」と呼んでいます。(抑揚は違いますが) 私は言語学を学んだことがないのですが、広東語も日本語も口の前半分、硬口蓋を使ったクリアーな音が多く、一方、普通語や米国英語は口の後半分、軟口蓋を使ったり、巻き舌のRをしたり、こもった音が多い気がします。
件のM君は、北方の「騎馬民族」(人種を問わず彼は北の方はこの度合が高いと言うのですが)は寒いところに住んでいるので口を余り開かないで話すようになったが、温暖・湿潤な南方で海に面した地域では口を開いて話すのでクリーンでクリアーな音になるといいます。
そういえば、オペラで聞くイタリア語なぞ、クリアーな綺麗な音ばかり、全然こもった音はしない気がします。M君の説が本当なら、やはり、ここにも黒潮文化圏と騎馬民族圏で言葉の音まで違うことになります。黒潮文化圏の言葉はクリーンでクリアーな硬口蓋の言語。独断と偏見に満ちた仮説を披露させて頂きました。
香港事情
1997年、香港返還の年のことでした。私は北角という地域にある「シティガーデン」というマンションのビクトリアハーバー側の部屋に住んでいました。景色が良かったせいもありますが、香港人の家主が流麗な英語を話し意思疎通がやりやすかったので選びました。お嬢さんがシドニーで学んでおり家族で豪州へ行っている間、香港の家を貸しているという人でした。
その頃、隣に別の家族が引っ越してきて、毎週末沢山の人が来て何時までもうるさいので、たまたま遊びに来た家主につぶやいたところ、彼女はこう言いました。「きっとメインランド(中国本土)の人ですよ。仕方ないですねえ。」
それから12年。いま、香港でこんなことを言えばバチがあたりますが、香港人は今でも「彼等」と言い「本土の人たち」と呼ぶでしょう。
意識は少しずつ変わってきていますが、底流に潜むものはそう簡単に変わらないのではないでしょうか。
2度目の駐在の時の住まいは九龍半島側の所謂サービスアパートメントで部屋の窓からは180度ビクトリアハーバーが見渡せる言わば長期滞在用ホテルマンションでした。入館の受付は何人もの管理人が居ましたが、ほぼ皆顔を覚えているようでした。
その頃、中国本土大好き人間のM君が部屋に遊びに来たのですが、特にインターホンが鳴るでもなし突然ドアをノックしたのです。
どうやって受付の管理人をクリアーしたのかと尋ねたら、いわく、「英語で言ったら大丈夫でした。普通語で言ったら多分止められたでしょうね。」と。
なるほど。おなじアジア人でありながら広東語や普通語ではなく、英語で切り出すのは日本人か韓国人、あとせいぜいシンガポール人だから。2003年か2004年のことだったと思いますが、これも香港の顔のひとつです。

中国はけっして一つではない。私のこの仮説に少し御賛同いただけるでしょうか? そして黒潮の海を通じて文化を同じくする人々が地域の安定と平和へベクトルを同じくすべきとの気持ちにも。
先月、5月26日、中国の共産党主席・胡錦涛と国民党主席・呉伯雄が台湾海峡をはさんだ中国の2地域間で関税撤廃を軸とした経済協力の枠組みを作っていくこと、更に軍事面での信頼醸成措置を講じ平和協定の締結に向かうことに合意したと報道されています。
詳しいことは未だわかりませんが、なだらかな United Federation of China に向けた動きとして注目されます。
国際政治学的にこの動きはとても重要ですが、私の言う黒潮文化圏と仲良くクロスオーバーして平和と豊饒の海が繁栄して欲しいものです。






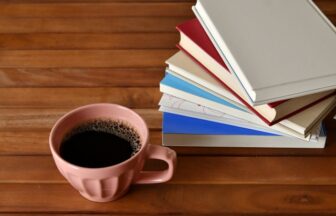


この記事へのコメントはありません。