マイアドバイザー® 池田龍也 (イケダ タツヤ)さん による月1回の連載コラムです。
目次
【第16回】 池田龍也 の ちょっと気になるニュースから 「中国の不動産バブルって?
~中国経済の先行きのカギを握る不動産市場~」
池田龍也⇒プロフィール
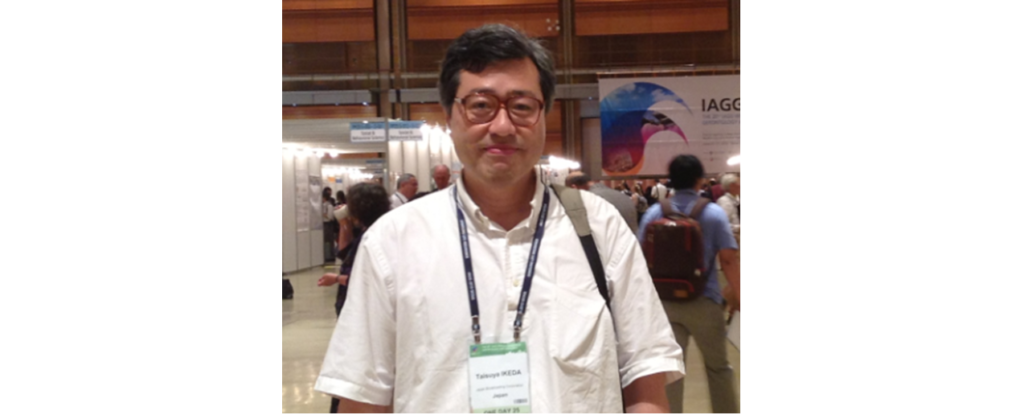
▼「潤日」(ルンリー)
今回の参議院議員選挙でも、「日本人ファースト」というキャッチコピーがさまざまなところで取り上げられ、メディアでも大きな議論になりました。日本に来ている外国人の扱いをどうするか、が選挙の大きな争点にもなっていました。
中国の富裕層が日本を目指して続々とやってきている、といいます。彼らを称して「潤日」。「潤」は、中国音でルン、run、逃げるとの連想で使われているそうです。「潤日」とは「日本へ逃げる」という意味になるのだそうです。
子弟の教育でも、中学受験から大学入試まで、日本の教育現場で、中国人の存在感が大きくなっています。タワーマンションなど日本の不動産市場でも中国人富裕層が目立ってきています。
中国人の観光客が大挙してやってきて銀座の大通りを行き来したり、薬や家電の量販店に殺到していたり、といういわゆる「爆買い」といわれた頃とは明らかに違い、時代は新たな局面になっているようです。
▼どうなっていくのか中国経済
中国の富裕層が、危機に敏感で、中国経済の先行きへの不安、あるいは中国経済の危機を、未然に察知して動いている結果が「潤日」なのか、あるいは単なる短期的な現象で、中国の一部の富裕層が、過剰反応を示しているだけなのか、現時点ではまだよくわからないところがあります。
前回は、トランプ関税問題に関連して「中国の存在感」、中国の経済発展の歴史を振り返ってみましたが、今回は引き続き中国についてです。今回は、中国経済が、いま、あるいはこれからどうなるのか、についてみてみたいと思います。中国の存在感が大きければ大きいほど、逆に、中国なしには世界経済を語れない時代になり、中国経済に何かあれば、世界経済が大きなダメージを受けることになりかねません。そういう意味でBIG CHINA(巨大な中国)は、そのまま裏返せば「BIG CHINA RISK(巨大な中国リスク)」につながります。
▼最近の中国経済のニュース、リポート
最近のニュースやリポートから中国経済の動向、分析を拾ってみると、以下のような感じになります。中国経済、堅調、好調というトーンのものはほとんどなく、いくつもの不安材料があるという分析であふれています。
・中国経済4~6月は5.2%成長、予想上回る-輸出好調も消費減速(7月15日ブルームバーグ)
・中国、景気先行きに警戒感 輸出前倒しの反動必至、消費にも不透明感(7月16日時事通信)
・日本より危険な中国の不動産バブル崩壊…目先の成長だけ追い求め「失われた数百年」到来か?
(7月14日ニューズウィーク日本版WEB)
・「中国の病」はもはや治療不可能…!大不況の元凶「住宅バブル崩壊」とついに訪れる「ゾンビ企業」
大量発生のヤバすぎる実態(6月25日講談社 現代ビジネスWEB)
・構造的課題を抱える中国経済(7月10日経団連タイムスWEB)
・中国の不動産危機はさらに悪化する可能性がある…ゴールドマン・サックスが分析
(7月11日 ヤフーニュース BUSINESS INSIDER)
・中国人民銀行が本格緩和、貿易協議を前に景気下支えを模索か(5月7日第一生命経済研究所)
・中国は不動産不況と米国リスクをどう乗り越えるか-相次ぎ発表される経済政策の現状評価と今後の見通し(2024年11月15日 ニッセイ基礎研究所)

▼中国経済の先行き、そのポイントはどこに
このようなニュースの記事やリポートで指摘されていることをまとめますと、だいたい、いくつかの論点に絞られてきます。
・不動産市場の下落(不動産バブル崩壊、という指摘も)
・若年層の高失業率
・デフレ
・消費者の購買意欲減退
・トランプ関税の影響(米中貿易戦争)
発展途上国の経済成長のステップには一つのパターンがあります。中国も同様で、かつての改革開放政策によって、外国の資本を受け入れ、外資の工場進出などを積極的に推し進め、国内の安い労働力を武器にして、輸出産業を育成、輸出主導型の経済成長を実現、さらには国民が豊かになって、国内市場も大きくなってきたという流れがあります。グローバル経済の時代を追い風にして大きくなってきた中国の成長モデルですが、この勝利の方程式が通用しなくなり、トランプ大統領の対中強硬姿勢がさらにそれに追い打ちをかけ、いま踊り場に来ているというのがおおかたの指摘のようです。
▼ 「中国不動産バブル」の論点
このあたりの事情を詳しく解説した本があります。「中国不動産バブル」という新書版で、中国の不動産バブルの発生から崩壊に至る経緯をわかりやすくひもといています。著者は中国出身のエコノミストで東京財団政策研究所主席研究員の柯隆氏、中国経済の分析や解説には定評があります。
資本主義ではない国、中国では土地は公有制で、土地の売買はできないのに、なぜ不動産バブルが発生したのか、という、そもそもから詳しく説明してくれていますので、この数十年の中国経済の発展の歴史を俯瞰させてくれます。
著者によると、まず、改革・開放、経済自由化の最初の難題は、土地の公有制を維持しながらどう開発を進めるのか、だったのだそうです。
そこで中国共産党は、都市開発、不動産開発を活性化するため、1990年代後半から定期借地権という形で、商業用地や宅地の使用権を払い下げていくことにしました。そして払い下げの売り上げを各々の市政府に帰属させたことで、地域の商業施設の整備は進み、地方政府は、使用権を払い下げた財源で、地下鉄などの交通網の整備も進めるという、都市開発、不動産開発主導型の経済発展を実現してきました。地方政府は、さらに地方債を発行したり、投資会社を設立して銀行から巨額の融資を受けたりしながら経済発展を実現してきました。
しかし、不動産、都市開発をエンジンにした経済成長は、不動産バブルの崩壊とともに逆回りを始めているということです。企業の債務超過、地方政府の財政赤字をどうするかが、いまや大きな課題になっているということです。地方の財政危機は、年金など社会保障にも影響し、人々の生活不安にもつながっているといいます。
▼ これからの中国は?
中国経済は、この3、40年、
・外資導入による輸出産業の育成、成長
・不動産開発をてこにした経済成長
この2つがうまくかみあって世界第二位の経済大国に躍り出たわけですが、米中貿易戦争で、外国資本がこれまでと同じように中国に殺到するかどうか、また中国にとどまるかは未知数ですし、輸出産業がこれからも成長していく保証はありません。トランプ政権の関税政策によってさらに先行きが極めて不透明になっていることは間違いありません。
また不動産開発を起爆剤にして成長を実現したやり方は、いまや不動産バブル崩壊で、逆に大きな負の遺産になりつつあるようです。
著書をご紹介した柯隆氏は「不動産バブル崩壊は40年続いた改革・開放政策の終わりの始まりを意味するのかもしれない」と述べています。








この記事へのコメントはありません。