マイアドバイザー® 顧問 岡本英夫 (オカモト ヒデオ)さん による月1回の連載コラムです。
ファイナンシャル・アドバイザー(近代セールス社;2022年春号以降休刊)の初代編集長として、同誌でも寄稿されていたエッセイの続編的な意味合いのあるコラムとなります。
今回は第6回目です。
岡本英夫⇒プロフィール

マイアドバイザー®の顧問をつとめられた故田中英之氏が提唱されたファイナンシャルプランニングのコンセプトのひとつに「ファミリープロテクション」がある。
田中さんからこの言葉を聞いたのは、1990年代のなかば頃だが、私自身、同じようなコンセプトでファイナンシャルプランニングのあり方を説明し、かつ実践していた。
ファミリープロテクションを直訳すれば「家族防衛」「家族保障」ということになるが、要は、ファイナンシャルプランニングは家族単位で考え、家族の生活を豊かにし、その生活を守ることだという考え方である。
家族の成長過程にしたがって、ファミリープロテクションを紹介してみたい。
目次
緊急予備資金(病気・けがへの備え)
ファイナンシャルプランニングは、「緊急予備資金」をつくることからはじまる。
なにはともあれ積立貯蓄である。
ますは月間生活費の3か月分を目標に貯蓄する。3か月分がたまれば、半年分、1年分と目標をアップしていく。1年分に達したら「緊急予備資金」としていつでも解約できる金融商品で固定する。
私事でいえば、最初は信用金庫の定期積金ではじめた。目標額は50万円だった。50万円に達した時点で定期預金とし、積立は継続した。
その繰り返しで数年後にいくばくかの投資資金もできた。積み立ては「一生の仕事」である。
一家の主の死(死亡・障害リスク)
結婚し、子供が誕生すれば、いざという時の家族の生活資金が気になりはじめる。
「一家の主の死」への対応である。
一家の柱である夫死亡後の生活費を見積もり、遺族年金などを差し引いて必要保険金額を算出、生命保険(定期保険等)で備える。ポイントは加齢により遺族生活資金は減少していくことだ。
この作業では、加入していた定期付終身保険を見直し、特約のない終身保険に切り替えた。以後、保険料払込期間満了の65歳まで死亡保障を見直す必要はなかった。
子どもの教育費(子育てリスク)
子どもの教育費は、当時予定利率の高かった「こども保険」で対応した。
高校、大学入学時、そして22歳の満期時に祝い金が出た。
現在の「こども保険」「学資保険」はかつてほどのメリットはないが、準備を怠って奨学金や教育ローンを利用するのであれば、加入したほうがよい。
住宅取得と住宅ローン(住宅取得リスク)
多くの場合住宅ローンを組んで、週十年にわたり返済を続けることになる。
資金計画を立て頭金を準備、ローンを組み、団体生命保険に加入する。
ポイントは毎月返済額を貯蓄が継続可能な額に抑え、家計に余裕を持たせることである。
30歳のとき65歳までの35年ローンを組んだが、一度借り換えを行い、一部繰上げ返済も行って55歳の時に完済した。
老後リスク(長生きリスク)
子供の成長に伴い老後の生活費が気になりはじめる。
「長生きリスク」への対応である。
40歳になるころ老齢年金額を試算し、必要な老後生活資金の準備に着手する。財形年金と60歳支給開始10年の個人年金保険を契約した。結果的には、65歳まで勤務したため、毎年の私的年金は投資に回した。
老後資金準備は「40歳代はコツコツと、子どもの独立する50歳半ばから一気に準備」である。
現在ならiDeCoや「つみたてNISA」だろうが、財形年金が勤務先にあれば、それも一手段である。
医療・成人病リスク
同じころに心配にあるのが、加齢に伴う成人病等のリスクである。
医療保険やがん保険への加入を考えるときには、健康保険の高額療養費や傷病手当金の知識も必要になる。
これらの知識は早くから得ていたから、医療保険には加入しなかった。
ただし、医療保険・がん保険が不要とは思っていない。必要と思うのであれば、加入したほうが安心である。
相続リスク
50歳台に入ると父母の健康状態が気になりはじめる。
介護リスクとともに、相続について考え始める。
父は10年近く療養したが、医療費は父の年金と相殺だった。相続時には、宅地、田畑とそこそこの金融資産が残っていたが、相続税はかからなかった。ただし。相続した不動産の取り扱いが課題となっている。
賠償責任リスク
40歳前後の出張の際、満員電車の網棚から手荷物が落ち、座席にいた女性を直撃した。病院まで同行したが大事には至らなかった。
これをきっかけに「賠償リスク」に備えるべく、個人賠償責任保険に加入した。
結局、特にリスクは顕在化せず60歳定年を迎えたが、定年後も65歳まで働くことができた。
年金は68歳まで繰り下げた。
今後は老いによるリスクが高まるが、ある程度は対応できていると考えている。
最後に・・・ 金融教育を国家政略に?
現在(執筆時点=2022年9月)、「金融教育を国家戦略に」と騒がれているが、金融教育ではなく人生の様々なリスクに対応する生活教育が必要なのではないか。
「貯蓄から投資へ」の掛け声は20年以上にわたって飽きるほど聞いてきたが、貯蓄があってこその投資ではないか?
「ファミリープロテクション」(家族防衛)教育のほうが、的を得ているような気がする。

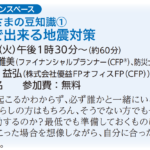







この記事へのコメントはありません。