【2013年 第10回 今月の数字10:10ヶ月以内にやらなくちゃ!?】
相続に関する数字エトセトラ
平川 すみこ ⇒プロフィール
 このコラムでは、相続に関して知っておきたい話題を毎月の数字に絡めてお伝えしていきます。
このコラムでは、相続に関して知っておきたい話題を毎月の数字に絡めてお伝えしていきます。
10月の数字は「10」。相続税の申告と納付は10ヶ月以内という期間制限が定められています。この長いようで短い10ヶ月の間にやっておくべきことはなんでしょうか?
そもそも相続税がかからず申告しなくてもよい場合があります。一方、相続税はかからないけれども申告が必要だという場合もあります。また申告期限までにやっておかないと多額の相続税を納付しなくてはならないといったこともあります。申告期限までの10ヶ月に何をやっておけばいいでしょうか。
■申告期限は10ヶ月以内
 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
一般的には「死亡したことを知った日」=「死亡した日」なので、例えば1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限(この期限が土、日、祝日等にあたるときは、これらの日の翌日)です。納めるべき相続税がある場合の納付期限も同じです。
つまり、この期限までに、相続税を算出するための相続財産を確認したり、誰がどの財産を相続するかを決めて相続税を計算し、納める相続税があれば納税準備をしておかなくてはいけませんね。そうはいっても、財産がどれだけあるのかすべて確認するのに手間取ったり、どのように分割するかがなかなか決まらずに期限を迎えてしまうこともあります。そのようなときは、申告期限を延長してもらえるでしょうか?
いいえ、申告期限の延長はできない(※)のです。相続財産が分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。相続財産の分割協議が成立していなくても各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
※一定の場合に期限後申告が認められますが、申告期限の延長を申請する必要があります。
■相続税の申告のやり直しができる!?
このように申告・納付期限は「まったなし!」ですから、期限内に申告・納付をしますが、その後に相続財産が見つかった!とか、誰が何を相続するか分割がようやく決まった!ということがあれば、相続税の申告のやり直しができるようになっています。
申告した相続税が少なすぎた(過少)の場合は、「修正申告」をして不足分の税額(加算税、延滞税が加算されることもあり)を納め、申告した相続税が多すぎた(過大)の場合は、「更正の請求(減額更正)」をして納付しすぎた税額を還付してもらいます。
「修正申告」は税務署から「更正」(納税額を誤っているので税務署が修正すること)されるまでできますが、「更正の請求」はできる請求期間に制限がありますので、ご注意ください。「更正の請求」については2013年5月のコラム「5年以内なら取り戻せる!?」にも記述しています。
■まずは相続財産の確認を!
遺言がなかったり、遺言で指定されているもの以外の相続財産がある場合は、相続人等でどのように分割するか協議をしますので、財産がどれだけあるのかきちんと確認しておく必要があります。あるはずと思っていた財産がなかったり(例:亡くなった方が生前中に売却していた)、知らない財産がでてきたり。財産が確認できていなければ分けるにも分けられないし、後から財産がみつかって協議をやり直したりという煩わしさも生じるでしょう。
税金面においても税負担が増えるかもしれません。相続税の申告をして納税した後に財産がでてきたとなると「修正申告」することになったり、税務署から指摘を受けることがあったりして、追徴課税で新たな税額分だけでなく過少申告加算税や延滞税等がかかる場合があるからです。
また、亡くなった方の負債(未払いの医療費や税金も含みます)で相続人が返済するものは、相続税の計算において財産から控除することができますので、どれくらい負債があるのかも確認しておきたいもの。(控除対象とならない負債もあります)
とはいえ、すべての相続財産をもれなく確認するのは相当な時間と労力がかかるし、通常では見つけきれない財産もあったりします。となると、お金を払って専門家に調査してもらう必要があるかもしれません。
そのような負担を家族にかけないためにも、財産を最も把握しているご本人が元気なうちに財産目録、一覧表を作成しておくのが望ましいでしょう。ご自身で表を作ったりできないということであれば、市販のエンディングノートに書き込んでいくのもよいでしょう。
■分割できていないと税負担が増える!?
現行の相続税法で相続税がかかるのは、年間死亡者数100人あたり4人程度です。相続税には基礎控除、配偶者の控除(税額軽減)、居住用宅地等の小規模宅地等の評価減といった大きな控除・特例があり、これらを適用すると相続税の負担が少なくなったり、ゼロになったりするのです。
このうち基礎控除は無条件で「5,000万円と法定相続人1人あたり1,000万円」が控除できるのですが、配偶者の控除(税額軽減)、小規模宅地等の評価額特例は分割されている財産にしか適用が受けられません。
これらの控除、特例を適用すれば相続税はうんと少なくて、あるいはゼロですむかもしれないのに、申告期限までに分割ができていないばかりに適用しないで算出した相続税額を納めなければいけません。分割見込の書類を提出した上で、申告期限から3年以内(やむを得ない事情があって税務署長の承認を受けた場合はさらに4ヶ月以内)に分割がされれば控除、特例が適用でき、「更正の請求」の申告をしてすでに納めた税金の還付を受けることができますが、一旦は多額の税額を納めておかないといけないことは相続人等にとって大きな負担になるでしょう。
このように税金面でも、申告期限までの10ヶ月の間に分割できることが望ましいので、相続人等がいかにもめることなく早期に分割できるかを考えておく必要がありますね。遺言でどのように分割するか指定されていれば、相続人等は協議する必要なく指定に従って分割できるでしょう。全員合意の上で遺言での指定と違う分割になるかもしれませんが、いずれにしろ遺言の内容をもとに早く分割がまとまると思われます。きちんと遺言で指定しておくことも財産を遺す方の責務といえるのではないでしょうか。
さて、10ヶ月以内にやらなくちゃというテーマでしたが、財産を遺す方が生前のお元気なうちに財産目録や遺言を作成しておいた方がより望ましいということでもあります。まだまだ先のことでしょうけれど、いつかは訪れる相続に備えて今から準備・対策を行っていくようにしましょう。
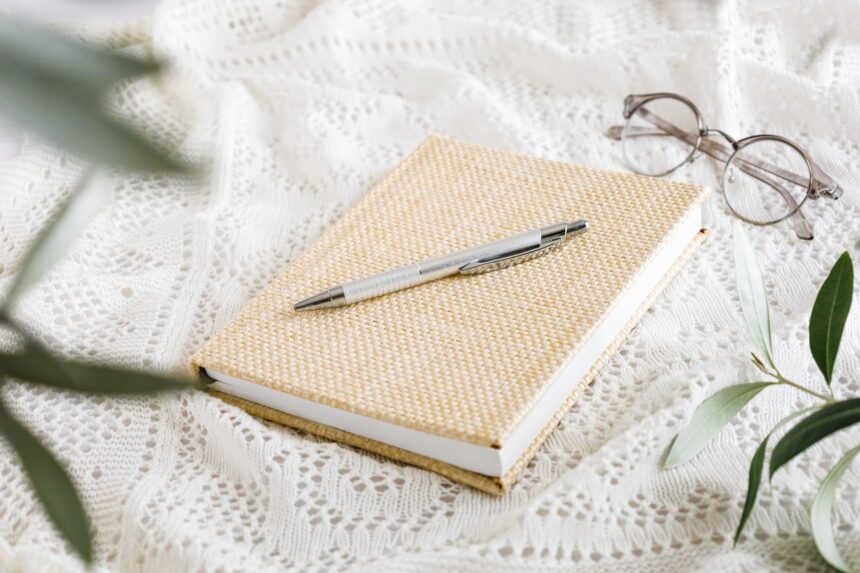








この記事へのコメントはありません。