生命保険業界の歴史を検証することで、将来への課題を探っていくコラムを連載していきたいと思います。
証券と保険をマスターすれば、FPとして一本立ちできると言われます。
なるほど、最も複雑で、顧客からのクレームの多い業界です。
一方で、無責任なマスコミ報道などにより間違ったイメージ・情報が定着した業過でもあります。
「へぇ~!!」と驚かれる一般には知られないエピソードを交えながら、正確な現状を確認する一助となれば幸いです。
第1回は、生命保険の誕生から第二次世界大戦前までの日本の生命保険業界を2回に分けて概観してみましょう。
まず、前編は「生命保険の誕生」についてです。
嶋田雅嗣⇒プロフィール

1.保険の歴史
保険の成り立ち
14世紀のイタリアでは、海上貿易が盛んになった。
航海が成功すれば莫大な利益を得たが、一方で巨大リスクもあった。
リスク分散のために、船主たちは、遭難や海賊に襲われた場合には、失われた船や積荷の価値だけは補償金が受取れる仕組みを作った。
これが、海上保険、ひいては損害保険の原型となる。
1866(慶応2)年に発生したロンドンの大火災では、都市の8割を焼失している。
これを機に、英国にて海上保険を応用した火災保険が編み出されている。
ちなみに、英国ロンドンのシティ(金融街)にある保険取引所「ロイズ」は、1688(元禄元)年頃にエドワード・ロイドがコーヒー・ハウスを開いたが、その店に保険業者たちが集まり、保険取引の場として利用していたことに由来する。
ロイドが死去したあと、取引の場を失った保険業者たちが資金を出し合い、新たにロイズ・コーヒー・ハウス(ロイドのコーヒー店)と名づけたコーヒー店を開いている。
時代とともにコーヒー・ハウスではなくなったが、ロイズ (Lloyd’s) という名前はそのまま残った。
ロイズと言えば、北海道のチョコレートメーカーのロイズ(ROYCE’)を思い浮かべるが、こちらは創業者・山崎泰博(やまざき やすひろ)の名前(やすひろ→ろひす・や)のアナグラム(単語または文の中の文字をいくつか入れ替えることによって、全く別の意味にさせる遊び)である。
生命保険の誕生
-
コレギア・テヌイオルム
太古の時代から、護身・食糧確保のために、人類は血縁集団、氏族社会という群れを作って集団生活をおこなっており、相互扶助と防衛は一種の義務であった。
古代ローマでは「コレギア・テヌイオルム」と呼ばれる相互扶助組合が市民の間で広まった。
組合員のうち誰かが亡くなると葬式代が給付される制度である。-
ギルド
中世ヨーロッパでは、商取引や貿易をおこなうにあたって、盗賊や海賊に襲われる危険を防御するため、自主的な団結と相互扶助を組織的におこなう制度「ギルド」がうまれた。
ギルドは、厳しい徒弟制度によって高い技術をもった親方しか参加することが出来ないしくみで、製品の品質や規格を統制していた。
同時に価格も統制していたため、商売の自由は制限されていた。そのかわりに、組合員の死亡の際は葬式代が支払われ、遺族の生活も組合が面倒をみている。
組合員の生存中にも、病気などの場合は組合が助け、材料の購入など生活の様々な面でギルドのメンバーは互いに助け合う仕組みを構築している。-
友愛組合
17世紀中頃になると、英国では、耕すべき土地も無く資本も持たない労働者が都市に集まってきた。
教会や、パブの常連客たちは、仲間うちに死者が出るたびに、帽子を回して弔慰金を集めた。
そのうちに、あらかじめお金を集めて貯めておくようになり、この組織は、「友愛組合」と呼ばれた。年齢によって掛け金を変えることをせず、全員が同額の掛け金を負担したため、構成員が高齢になると資金不足になってしまうものが多かった。
その後、近代的な生命保険制度の発達に合わせ、生命保険会社に対する共済組合のような形で進化しながら、現在でも192組合が存続している。-
香典前払組合
17世紀後半、英国のセントポール寺院の牧師たちの間で「香典前払組合」が設立された。掛金は年齢を問わず一律であったため、高齢者は短期間の加入で済むため得するが、若年者は長く掛金を払うことになり、不公平感は否めなかった。-
アミカブル・ソサエティ
1699(元禄12)年、寡婦と孤児のための保険組合が設立された。
1706(宝永3)年には、最初の生命保険会社と言われる「アミカブル・ソサエティ」が創設された。
アミカブルとは、「親愛な」という意味で、発足当初から2,000人の組合員を集めることができた。
掛金は年齢、健康状態に関係無く、一律年5ポンドで、加入年齢は12歳以上55歳とし、分配は掛金総額の6分の5をその年に亡くなった人の人数で割るというものであった(6分の1は積立金として残した)。しかし、当然のことながら、死亡者数は毎年均一でないため、給付金は一定せず遺族の中に不公平感が生じる。
改善策として、後に加入年齢を45歳までに制限している。
-
ハレー
ハレー彗星の発見者である英国の天文学者エドモンド・ハレーは、所属していたロンドン王立協会から、人の寿命を数学的に研究することを依頼された。
人口の流入出の少なかったブレスラウ市(当時ドイツ、現在はポーランド)の墓誌等の資料を分析し、初めて死亡率に関する論文を発表している。この頃、すでに「大数の法則」が発見されており、これに死亡率も当てはまるとし、生命保険や終身年金の保険料は、加入時の年齢に応じて変えるべきと理論展開している。
-
ジェームズ・ドドソン
英国の数学者であったジェームズ・ドドソンは、「アミカブル・ソサエティ」に加入しようとしたが、46歳に達していた。
すでに加入可能年齢を45歳までに引き下げていたため加入を断られてしまう。
どういう断られ方をしたのかは不明であるが、怒り心頭であったであろうドドソンは、ハレーの論文を詳細に分析し、初めて「平準保険料」という概念を発表している。これまでよくあったように保険金が必要になりそうな年齢になってから駆け込みで加入するのではなく、長期間加入することを前提に、保険料の方は、毎年必要な金額の総計を死亡表から推定される加入年月で割ることで、保険料の急激な上昇を避けられる。
また、一旦決められた保険料は、毎年変わらないという現在の生命保険料数理の基礎となるものである。ドドソンは、この平準払保険料を採用した新たな生命保険組合を作ろうとしたが、認可が下りないまま、「アミカブル・ソサエティ」に加入を断られた。
翌年、わずか47歳で病死している。-
エクイタブル・ソサエティ
1762(宝暦12)年、ドドソンの平準払保険料を採用した「エクイタブル・ソサエティ」が誕生した。
年齢別の平準保険料、医的診査の実施、最高保険金額の制限、解約返戻金および契約者配当の実施、アクチュアリーの設置、定期保険以外に終身保険を販売するなど、近代生命保険の基礎となる仕組みのほとんどを採用している。
以後、これに倣った生命保険会社が相次いで設立されることになる。平準保険料方式では、契約期間の前半に将来の保険料を前払いし(この前払いした保険料がいわゆる責任準備金となる)、契約期間の後半に積み立てられた金額を保険料として取り崩すことになる。
これが現在の生命保険の保険料計算の主流となっている。本来、相互扶助の仕組みであった生命保険だが、平準保険料の採用により、前払いされた保険料が生命保険会社の多額の運用資産となった。
そして、いわゆる機関投資家として金融市場に大きな影響力を持つ礎となった。また、米国では、契約者間の公平性を強化する様々な法律の制定、新商品の開発が行われ、現在の近代生命保険事業の礎を固めている。
-
簡易保険
当初の生命保険は、資産家や牧師など特殊な人々のものであった。
ところが、産業革命により、都市生活者や給与所得者が急増すると一家の収入の稼ぎ手が亡くなった場合の生活保障や、葬儀費用などが問題となった。
19世紀半ばのことである。そこでロンドンの労働者達が、生命保険会社「プルーデンシャル ローン&保険組合」(現イギリス・プルーデンシャル)に少額な保険料で葬儀費用を賄える保険を作って欲しいと申し入れ、プルーデンシャルはこれを受け入れて少額・保険料建・週払の労働者保険を開発した。
これにより、生命保険は一挙に庶民のものとなった。
一時期、英国の全世帯の1/3がプルーデンシャルと契約していたとも言われている。当時の労働者にとってこうした問題がいかに深刻であったかを物語る事例といえよう。
こうした問題は現在の先進国各国で問題となっており、カナダでは国策として生命保険会社を整備した。
国会の議決により労働者向けの生命保険を扱う保険会社「マニュファクチャラーズ生命」を1887(明治20)年に設立している。
これが現在のマニュライフ生命保険である。
初代社長、サー・ジョン・A・マクドナルド卿は、同時にカナダの初代(および第3代)首相という2つの要職に就いていたことでも知られている。米国では、1875(明治8)年、「プルデンシャル・フレンドリー・ソサエティー」が創業した。
当時のアメリカは、経済恐慌とそれに続く不況の時代で、移民の大量流入により都市はスラムと化し、その不衛生な生活環境では死亡率も極めて高かった。
貧しく悲惨な生活を強いられており、家族の埋葬費を捻出することさえ困難な状況にあった。米国でも当時の生命保険は保険料・保険金とも高額で、一握りの裕福な上流階級の人々が加入しているにすぎなかった。
社会の切実なニーズにこたえるため、イギリスで普及していた労働者保険の導入に尽力し、「3cents A Week」週に3セントという非常に安い保険料で加入できる保険をアメリカではじめて販売した。-
生損保兼営禁止
米国では、18世紀末に入ると経済成長と共に保険事業も急成長を遂げた。
当時は生損保の兼営が認められており,生命保険事業免許を有する多くの保険会社が,火災保険または海上保険も扱っていた。1835(天保6)年12月にニューヨーク市に大火災が発生し,3日聞で市の中心部にある648棟が焼失し損害額は1,800万ドルに達した。
その影響で当時ニューヨーク州内にあった26社の保険会社のうち23社が破産した。1849(嘉永2)年に「保険会社の設立に関する一般法」が制定され、生損保兼営が実質禁止となった。
1871(明治4)年10月に起きたシカゴ大火災は,生命保険と火災保険の分離をさらに強める契機になった。
この火災により10万人が家を失い,市の3分の2の建物が焼失、損害額は1億7,500万ドルに達したが、そのうち9,600万ドルが保険によりてん補された。
結果,シカゴで事業を行っていた保険会社200社のうち68社が破産している。1940(昭和15)年ニューヨーク保険法によって,保険会社を生命保険会社、災害保険会社、火災保険会社に類別され、古くから存在する一部の既得権益を除き、3分類間での兼営が禁じられている。
この経緯にならい、日本でも生損保兼営は、黎明期を除き、禁止されている。
実質的な生損保兼営は、1996(平成8)年4月の改正保険業法の施行に伴う、生命保険子会社、損保子会社の設立まで時間を要することになる。
-

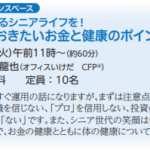



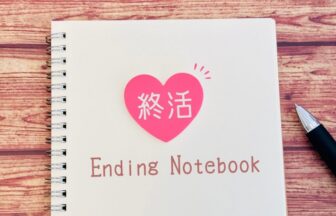
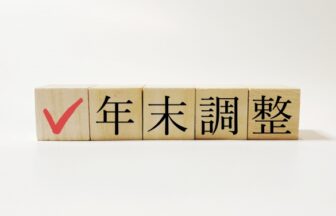


この記事へのコメントはありません。