0マイアドバイザー® 顧問 岡本英夫 (オカモト ヒデオ)さん による月1回の連載コラムです。
ファイナンシャル・アドバイザー(近代セールス社;2022年春号以降休刊)の初代編集長として、同誌でも寄稿されていたエッセイの続編的な意味合いのあるコラムとなります。
今回は第9回目です。
岡本英夫⇒プロフィール

12月中旬に発表される令和5年度の与党税制改正大綱ではNISAの恒久化などが織り込まれる予定である。
NISA制度自体が2014年の創設以降毎年のように変更されるため、制度理解が悩ましいと感じているFPも多かったと思う。
原因は、NISAが時限立法に基づく制度であったことにある。恒久化となればわかりやすくなるはずだ。
NISAのモデルとなった英国のISAが誕生したのは1999年4月のことだが、当初は10年間の期限が設けられていた。
それが、創設から7年目に恒久化され、その後も年間の拠出限度額が引き上げるなどの改正が行われた。
わが国もNISA創設から9年を経過しており、恒久化への移行は必然だともいえる。
今回は、NISAのこれまでを振り返ってみたい。
現行のNISAは2014年に取り扱いが開始された一般NISA、2016年1月に口座の申し込みがスタートしたジュニア NISA、そして2018年1月から投資が可能となったつみたてNISAが併存している。
NISA(成人NISA一般NISA)
NISAは「非課税口座内の少額上場株式等にかかる配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」のこと。
上場株式や株式投資信託にかかる個人の税金は2013年12月までは10%の軽減税率が適用されていたが、2014年1月から本則の20%課税となった(復興特別所得税を除く)。
これに対応するための激変緩和措置として導入されたのが、NISAである。
構想から2014年の制度創設まで・・・
NISAは平成21(2009)年度税制改正大綱で英国のISAをモデルにした「日本版ISA」として創設案が盛り込まれたが、このときから上場株式等の軽減税率10%の廃止と同時実施(当時の大綱では2012年から)とされていた。
2009年8月に政権は自民党から民主党に移ったが、非課税期間の短縮等の修正は行われたものの案自体は引き継がれた。
ただし・・・リーマンショック、東日本大震災後の株価低迷もあって10%の軽減税率は延長を余儀なくされ、日本版ISAの導入も延期された。
そして、2012年の自民党の政権復帰後の2013年税制改正で、2014年1月からの軽減税率廃止とNISAの実施が決まったのである。
2014年改正
NISAは、スタート直後から証券会社が口座獲得に力を注いだが、銀行等は及び腰であった。
スタート時の制度では、1人につき1つの金融機関で1つの口座しか開設できなかった。
出遅れた銀行等の金融機関は以後4年間、NISA口座の獲得ができなくなった。
2014年の税制改正では、2015年1月1日からNISA口座を開設する金融機関を変更できることにした。
これにより出遅れていた金融機関も顧客に対応できるようになった。
筆者は、ネット証券で口座を開設したが、投資に関しては当該株式の推移を見ながら投資した。
5年後にロールオーバーしたが、初年度の投資はそれなりの成果を得た。
2015年改正
2015年の税制改正では、年間投資上限額が100万円から120万円に引き上げられ、2016年1月から実施された。
年間120万円という金額は毎月10万年ずつ12か月間、定額で積み立てることを想定した金額だと説明された。
これにより5年間では最大600万円まで非課税で投資できることとなった。
ジュニアNISAの創設
2015年税制改正では、0歳から20歳までの未成年者を対象としたジュニアNISAが創設され、2016年1月1日から口座開設の申し込みが、同年4月1日から投資ができることになった。
年間投資上限額は80万円で、5年間で最大400万円まで投資できる。
0歳児などが自分で投資することはできないが、両親が子供の名義で投資を行う。
投資資金は親や祖父母からの贈与によるものがほとんどで、通常の暦年贈与(年間1人110万円まで非課税)が前提になる。
ジュニアNISAは口座開設手続き等が煩雑であることに加えて、基本的に18歳になるまでお金を引き出すことができない。
このため、大学の入学資金など長期投資が前提となることもあって、使い勝手は決して良いとは言えなかった。
このため、2020年度税制改正で、「利用実績が乏しいことから期間を延長せず、新規の口座開設を予定通り2023年までとする」「ジュニアNISAの終了に合わせ、2024年4月1日以後は(略)「払い出すことができることとする」とされた。
これにより2024年以後は18歳に達していなくても払い出しが可能になった。
筆者は、2016年当時0歳の孫名義のジュニアNISA資金を子(父親)に提供したが、2024年以降は、好きな時に払い出しができるわけで、既存利用者に限られるものの、この改正は朗報といえる。
2017年税制改正
2017年の税制改正では、2018年1月からつみたてNISA が創設されることとなった。
つみたてNISAは一般NISAとの選択制で、20歳以上(2023年以降は18歳以上)の個人がどちらかを選べる。
年間投資限度額は40万円で非課税期間は積み立てを行った年からそれぞれ20年間である。
2020年改正、そして…
以上が現行のNISAだが、2020年の税制改正により2024年からは2階建ての新NISA制度に移行することになっていることは、ご存知のとおりである。
12月中に発表される令和5(2023)年度税制改正大綱の内容が注目されるが、その内容については、次回、取り上げてみたい。

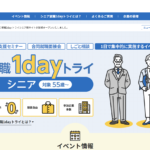







この記事へのコメントはありません。